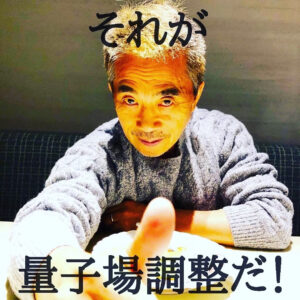「掃」は祓い清める、「除」はあまねくを意味し、掃除は神聖な場所、神と人がまみえる聖なる場所を余すところなくすべてを清めることを意味します。
「掃く」という字は手へんに「帚」という字を書きます。「帚」は棒の先端に細かい枝葉などを束ねて取り付けたもので、古代中国では、お酒をふりかけるなどして、廟(祖先の靈をまつる建物)を祓い清めるのに使ったといいます。
「ほうき」は「箒」と書き、古くは「ははき」と言ったそうです。日本最古の歴史書『古事記』や『万葉集』にも「帚持(ははきもち)」「玉箒(たまははき・たまばはき)」という名で登場します。
最澄いろりサイトより
『古事記』では、葦原中国(あしはらなかつくに)の平定に乗り出した天照大神が第二の使者として派遣した天若日子(あめのわかひこ)が、大国主神に国譲りを迫るために地上に降り立ちますが、大国主神の娘・下照比売(したてるひめ)と恋に落ち、結婚をしてしまいます。なかなか戻ってこない天若日子にしびれをきらした天照大神が、キジの鳴女(なきめ)を送り込みますが、天若日子はそのキジを射殺。それを知った天照大神が「もし天若日子に邪心があれば、当たれ」とその矢を突き返したところ、天若日子の胸を貫き死んでしまいます。「帚持」は、この天若日子のお葬式の場面で「鷺(さぎ)を帚持と為」(鷺がほうきを持つ役目として)と出てきます。
また、『万葉集』では“初春の 初子(はつね)の今日(けふ)の玉箒 手に取るからに 揺らぐ玉の緒”~大伴家持『万葉集 巻二十』~とあり、初春の今日、玉飾りをしたほうきを手に取ると玉飾りが揺れて、よろこばしく音をたてるという内容の歌に「玉箒」があります。758(天平宝字2)年正月3日の初子の儀式に、孝謙天皇が侍従・竪子・王臣たちを召して、内裏の東屋の垣の下に伺候させ、「玉箒」をさずけて宴を催した際の大伴家持の歌です。「玉箒」は本来養蚕の床を掃く道具だそうですが、ここで詠まれている「玉箒」は、儀式用のものだそうです。「玉箒」を揺らすと玉(魂)が活発になり邪気を払うと考えられていたと言います。
正倉院には、まさに758(天平宝字2)年正月初子の日の儀式で用いた「子日目利箒(ねのひのめとぎほうき)」という「ほうき」が残っています。古代中国の制にならい、蚕室を掃き清め蚕神を祀ったそうです。古代では“はらいきよめる”ということに使用され、掃除道具というより祭祀の道具としての意味が強かったようですね。
お掃除をすると氣持ちよくなるのは、このように「祓い清める」という行為だからなのだと、語源を調べて納得しました。
「祓い清める」というと、神社が思い浮かびますが、まさしくきれいに掃き掃除された神社は、スッキリしていますよね。
それこそパワースポットです。
そして、語源を知って、改めてお掃除を志事にしてよかった。と心から思いました。
志事としてでなくても、やっぱりお掃除をすると氣持ちが軽やかになりますよね。
5月、風が氣持ちよく窓を開けてお掃除するのにとてもいい季節です。
おうちをパワースポットにしましょう!

遠隔で量子場調整と空間ヒーリング